主な文化財
木造阿弥陀如来坐像(もくぞうあみだにょらいざぞう)
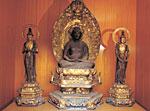
和泉の泉福寺にある阿弥陀如来坐像は、たいへん貴重なもので、国の重要文化財に指定されています。両脇には観音菩薩と勢至菩薩の脇侍があって、こちらは県指定の有形文化財です。
阿弥陀如来坐像は、平安末期から鎌倉初期にかけての作品で、定朝(じょうちょう)の様式を持つ当時の最高傑作といわれています。つくられた時期は確定できませんが、体内に残された修復銘から建長6年(1254年)に解体修理されたことがわかりました。
慶徳寺四天王像(けいとくじしてんのうぞう)

慶徳寺は曹洞宗の禅寺。四天王門は、本来薬師堂の門であったようですが、今は寺の総門となっています。
四天王は仏法を護持し、信者を守るといわれ、東方持国天、西方広目天、南方増長天、北方多聞天(毘沙門天)です。寄木造りで江戸時代中期の作と思われます。
薬師堂(やくしどう)

中武蔵寅薬師72番札所。薬師堂は、薬師如来をまつり、古くから「加田(がだ)のお薬師様」として近隣の信者を集め、心と身体の病の眼力を表わすといわれ、特に眼病にご利益があるといわれています。
堂内には、目にまつわる絵馬が数多く掛けられています。
薬師堂の天井には、陰山道益の筆による龍の絵と、優雅な天女が描かれています。
五厘沼窯跡(ごりんぬまかまあと)

古墳時代に造られた県内最古級の須恵器(すえき)窯跡。五厘沼と呼ばれている沼に向かって斜面に掘られた登窯です。岩盤を幅2~2.5メートル、高さ1.5~1.7メートルくらいで長さ15メートルほど掘り、トンネルのようにして斜面なりに上に登っています。現在砂で埋め戻して保存しています。
伊古乃速御玉比売神社(いこのはやみたまひめじんじゃ)

昔は二ノ宮山山頂にあったが文明元年(1469年)現在地に遷座したと伝えられています。
平安時代に編纂された延喜式神名帳に記載された古社の1つであり比企総社となっています。
境内全域に自生する樹木は、南半部にアラガシを主とする暖帯常緑樹、北半部はアカシデ、ソロを主とする温帯落葉樹で両樹帯が相生していて学術上きわめて重要なため、昭和3年に県指定の天然記念物になっています。勝海舟が神社号を大書した長さ11メートルののぼり旗1対があります。
羽尾道祖神(はねおどうそじん)

道祖神は「ドウロクジン」「サイノカミ」などと呼ばれ、村境を守る神、道の神、旅人を守る神、安産の神など、ところによってさまざまに考えられ信仰されています。道祖神には天然石を祀るもの、「道祖神」と文字を刻むものなどもあります。羽尾の道祖神は、双体(そうたい)道祖神(どうそじん)と呼ばれるもので、宝暦十年銘(1760年)があります。男女の神像が向合い、互いに手をつないでいます。今でも足の悪い人が願をかけ、足が治ると履物を供えるという信仰がおこなわれています。
福田馬頭観音(ふくだばとうかんのん)

伝承では宝亀9年(778年)白髪の老僧が当地で百日の祈願を行い、この願いを馬頭明王が聞き入れてくれました。ご加護のお礼に晴照庵を造り、自作の馬頭観音像を安置したと言われています。
人々には福田の観音様と親しみを込めて呼ばれています。毎年3月19日は縁日であり、昔は馬を飼っている人は馬を連れてお参りをし、帰りには自分の馬とよく似た絵馬を買って帰ったといいます。
福正寺勢至堂(ふくしょうじせいしどう)

福正寺の勢至堂で三夜様とも言われています。
この勢至菩薩はその昔、月輪大納言藤原兼実(かねざね)公が常に尊崇礼拝していたと伝えられ、午歳生まれの守り本尊として福徳円満開運出世、又安産や火防などに霊験があるといわれます。堂の創建は建久7年(1196年)と伝えられています。
堂前には、狛犬ではなく珍しい狛ウサギが参拝者を迎えます。
この記事に関するお問い合わせ先
教育委員会事務局 文化財保護担当
〒355-0803
埼玉県比企郡滑川町大字福田763-4
電話番号:0493-57-1902
お問い合わせはこちら












更新日:2021年03月03日